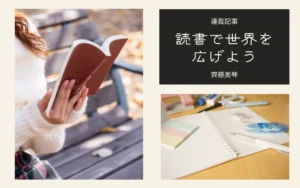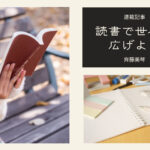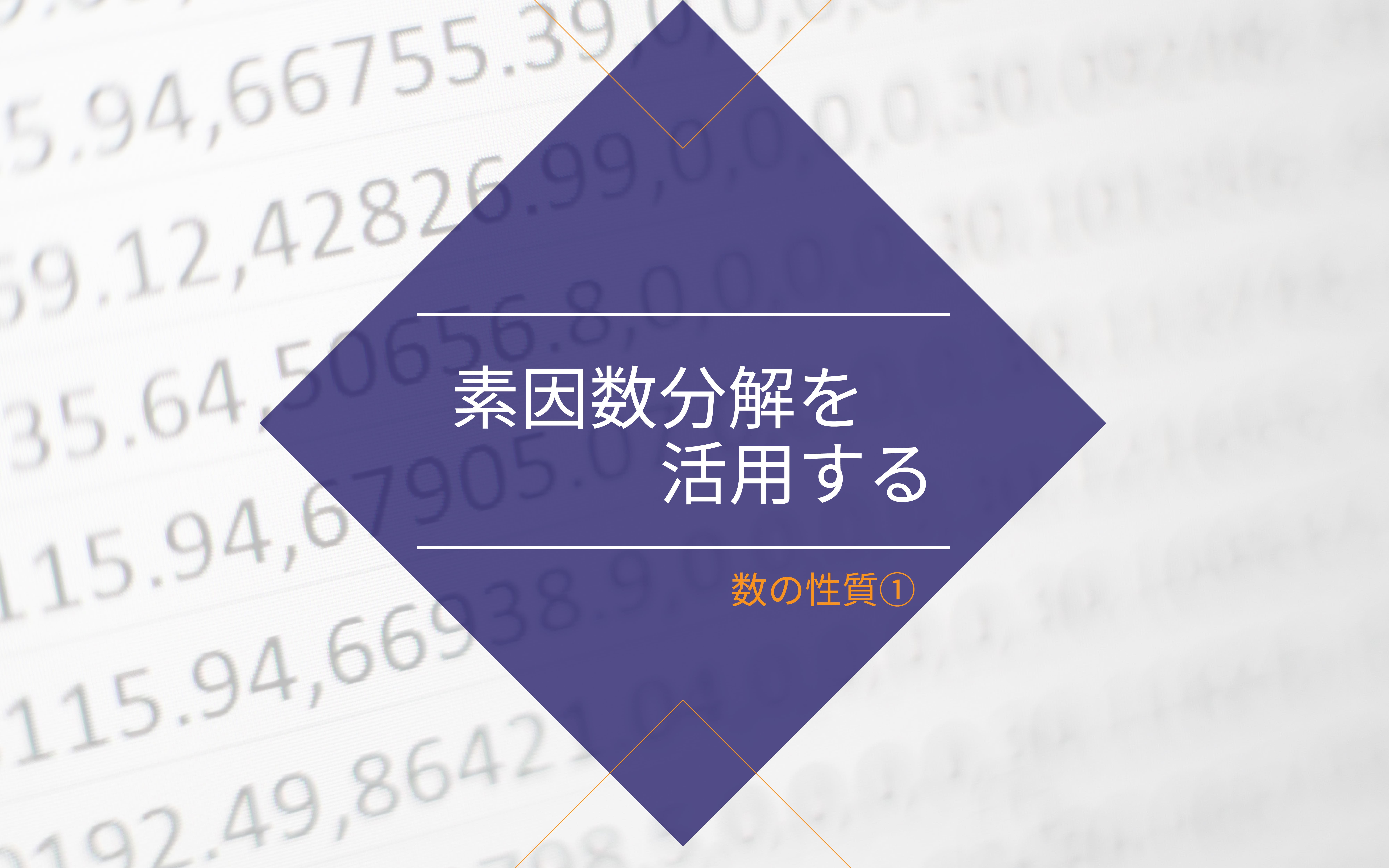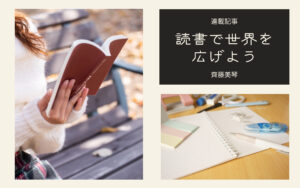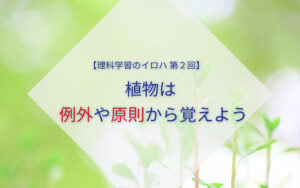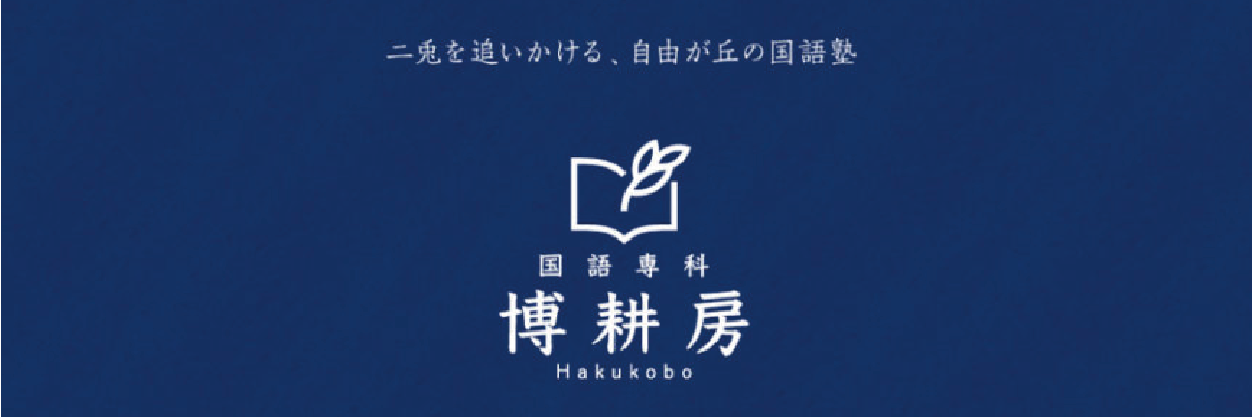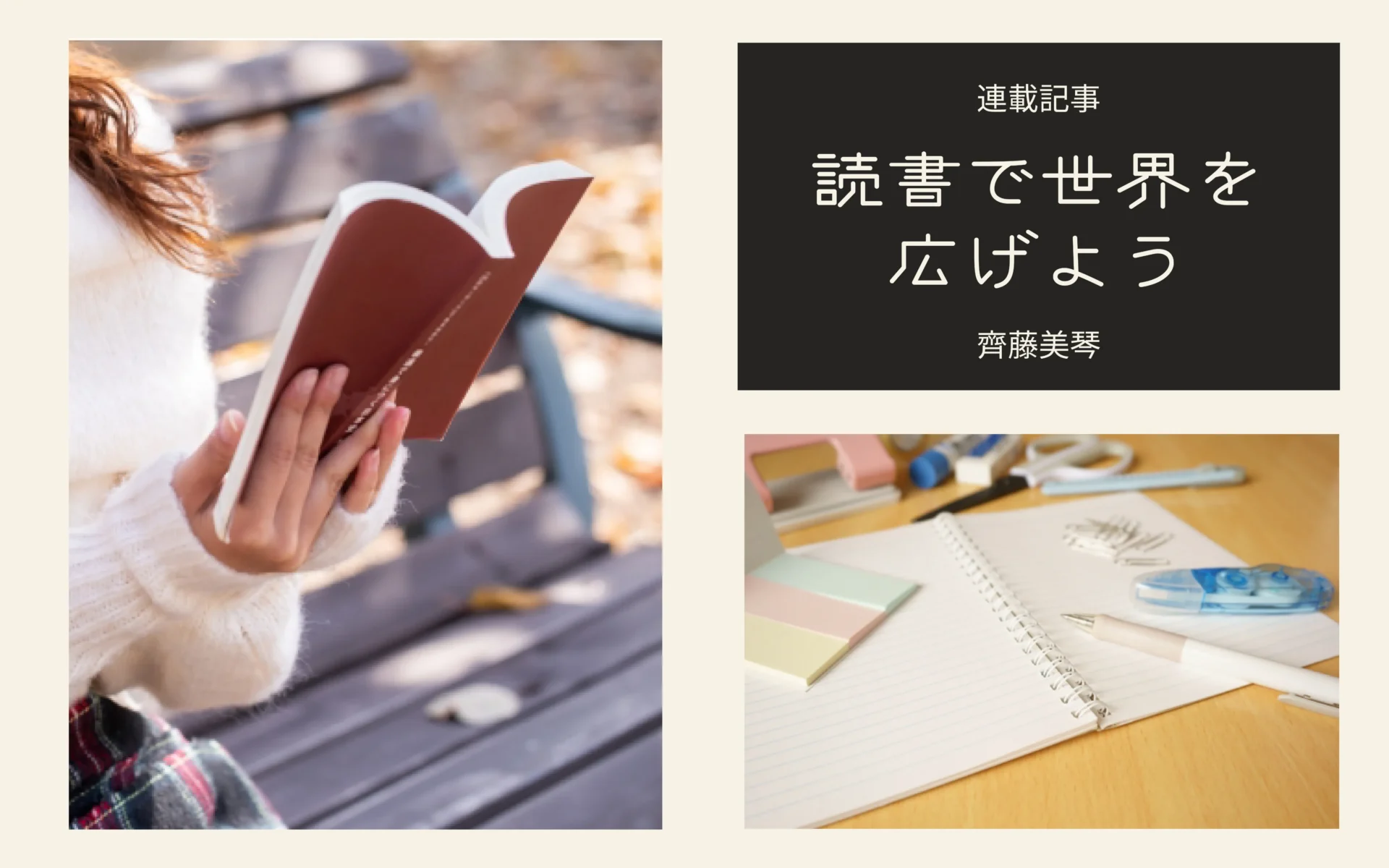
言葉の熱いバトル、俳句甲子園
9月に入っても厳しい残暑が続いています。今回は夏を振り返り、8月に愛媛県松山市で行われた「俳句甲子園」にまつわる物語を紹介します。
松山の地で、高校生たちが十七音を通して自分の世界を表現し合う「俳句甲子園」
俳句甲子園というものをご存じでしょうか。
甲子園という言葉で連想されるのは、まずは兵庫県の甲子園球場で行われる野球の大会ですが、やがて高校生の熱い夏の象徴として使われるようになり、今や野球以外もダンスや写真など様々な分野での甲子園が開催されています。
▼全国高等学校俳句選手権大会(俳句甲子園)
https://haikukoushien.com/
「俳句甲子園」は、高校生たちが五・七・五のわずか十七音で自分の世界を表現し合う、全国大会です。毎年夏、正岡子規にゆかりのある松山市で開催され、各地の予選を勝ち抜いたチームが集います。
スポーツさながらの青春の熱が感じられる大会
特徴的なのは、ただ俳句を詠むだけでなく「鑑賞とディベート」が勝敗を分ける点。句の解釈をめぐって言葉を交わし、審査員や観客の前で自分たちの感性をぶつけ合うのです。
そんな「俳句甲子園」を舞台にした小説や、俳句を重要なモチーフに据えた物語も少なくありません。限られた言葉が描き出す世界に、自分を重ねる登場人物たち。そこには、俳句という表現を通して見えてくる、青春のきらめきや葛藤が描かれています。
森谷明子 『南風吹く』
森谷明子さんの小説『南吹く』は、まさに俳句甲子園を目指す高校生たちの物語です。
舞台は瀬戸内海に浮かぶ小さな島・五木島。過疎が進み、主人公の航太の通う高校も再来年には廃校を迎える運命にあります。
航太は、家業の和菓子屋を継ぐことを父に否定され、怪我をして高校最後のバスケットボールの大会にも出られないことになり、と、行き場をなくした思いを抱えていました。あてもなく日々を過ごしていた彼を俳句甲子園へと誘ったのは、同級生の日向子。さらに漁師の息子の恵一、神主の息子の和彦や個性豊かな後輩たちを仲間に引き込み、チームはようやく形を整えます。
臨場感あふれる言葉の戦い
物語の魅力は、彼らが臨む俳句甲子園の緊張感あふれる試合の場面です。
与えられた課題句を前に、わずか三十秒で論を組み立て、審査員や観客を納得させなければならない――思考が駆け巡り、言葉を探し当てるまでの緊迫した流れが、まるで頭の中をそのまま追体験するかのように描かれます。
外からの目線が読者を惹きつける
航太達のチームは、全員が心ひとつに大会に出たいと思っていたわけではない寄せ集めのメンバーです。
でも、そういった外からの目線があるからこそ、俳句を知らない読者であっても自然と引き込まれていくのかもしれません。自らの感性や言葉の力に気づき、俳句だからこそ表現できることを模索していく過程も読みどころです。
青春小説×スポーツ小説の魅力を味わえる一冊
過疎化する島に住む高校生たちには、当然将来への不安や閉塞感もあることでしょう。そのような中で言葉に居場所を見つけ、仲間とともに挑む姿を描いた本作は、青春小説とスポーツ小説の両方の魅力を味わえる一冊です。
未来への希望も不安もすべてを込めて挑む「言葉の戦場」での真剣勝負。短い俳句に込められた広がりを読み解くやり取りには、言葉の奥深さと同時に、高校生ならではのまっすぐな感受性があふれています。
岸本葉子『俳句、はじめました』
最後に、本作を読んで俳句っておもしろいな、もう少し深く知りたいなと思った方におすすめのエッセイを紹介します。
岸本葉子さんの『俳句、はじめました』は、今や俳句歴15年以上になる岸本さんが、二度とない初心のときの「リアル」を文字にして残しておきたいと書かれたエッセイです。
俳句を詠むことは日常を五・七・五に託す体験である
俳句の経験が浅い立場から句会に参加し、先輩たちに学びながら感じた戸惑いや気づきを率直に綴っています。俳句を詠むことは難解な技術ではなく、日常の中の小さな出来事や感情を五・七・五に託す体験であることが伝わってきます。
初心者ならではの視点だからこそ、同じ入口に立つ読者に寄り添う温かさが感じられ、肩の力を抜いて俳句の世界に触れることができます。この本をきっかけに、俳句を詠んでみようかなという方が増えたらいいなと思いご紹介しました。