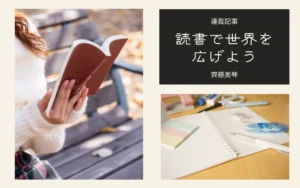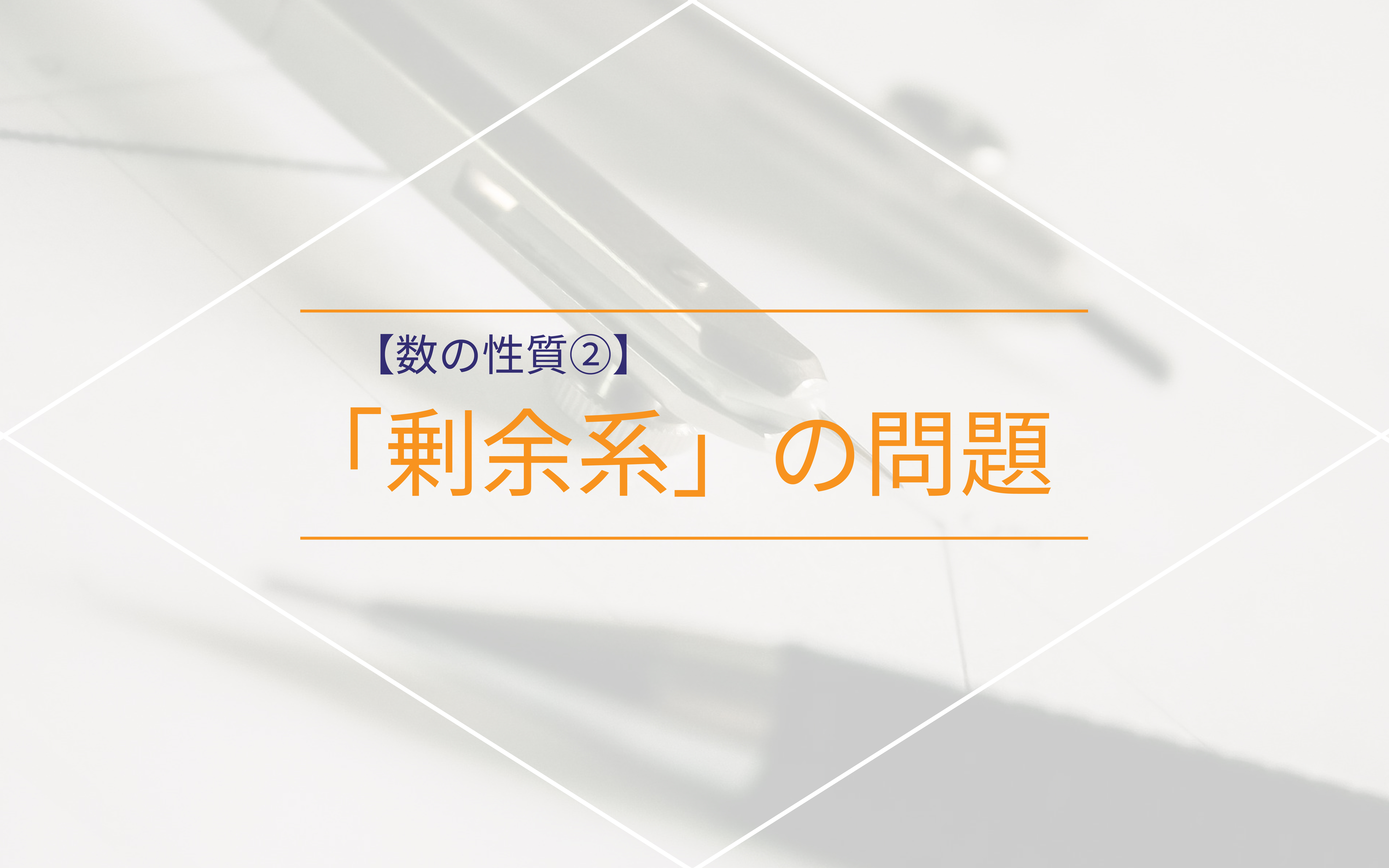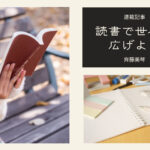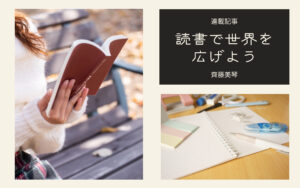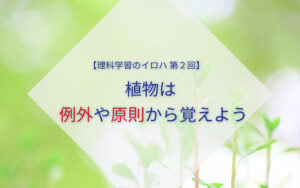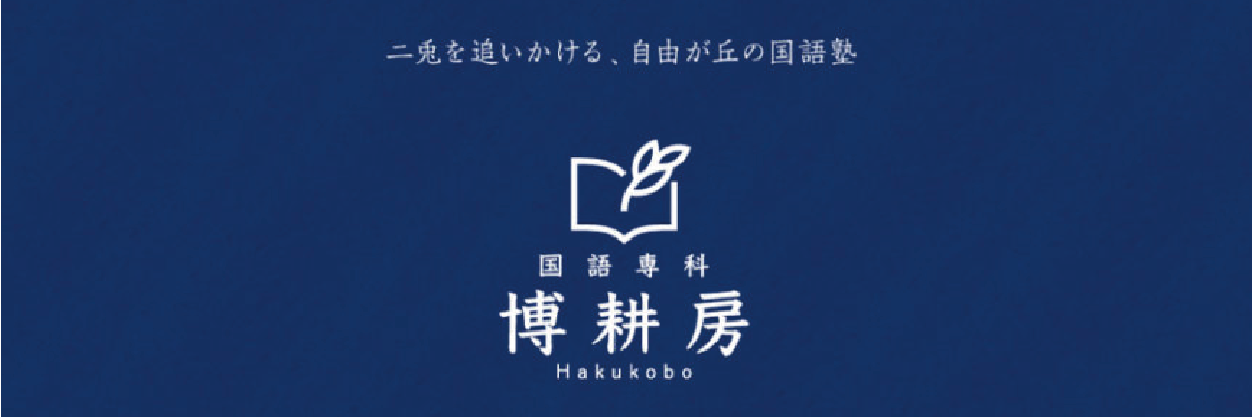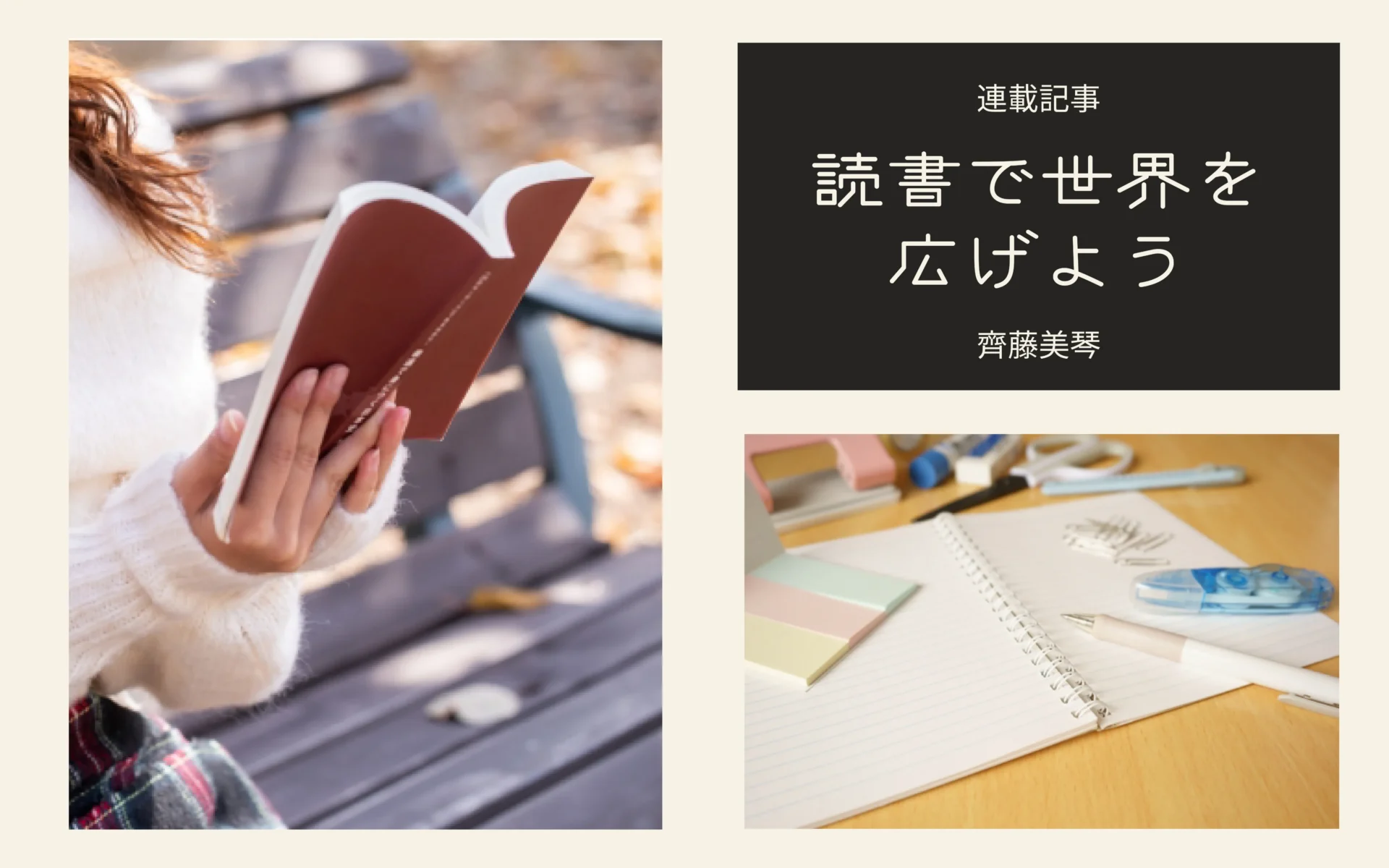
2025年6月刊行、長谷川まりるさんの新刊
今回は今注目を集めている作家である長谷川まりるさんの2025年6月に出たばかりの新刊、『この世は生きる価値がある』を紹介します。
長谷川さんは2018年に『お絵かき禁止の国』で第59回講談社児童文学新人賞佳作を受賞してデビューされました。LGBTに対して今ほど理解が進んでいなかった中、YA(ヤングアダルト)向けの本として書かれたということでも話題になりました。
一人称で語られるリアルな心情
デビュー作も今回の本もそうなのですが、長谷川さんの本は主人公の一人称で書かれることが多く、心情の吐露がとてもリアルです。特に主人公が抱える葛藤や迷い、不安は、三人称よりも一人称のほうが生々しく伝わります。
物語の語り手と読者の距離がぐっと近くなることで、読み手はあたかも自分自身がその物語を体験しているように感じやすくなりますし、子どもにとっての読みやすさを左右し、読書体験を「没入型」にしてくれる要素でもあります。
主人公に名前がない!?
何者かに追われ、必死で逃げる様子が描かれるプロローグ。今回の作品は、人間としての人生を送ったことのない「魂」が主人公という、フィクションならではのユニークな設定から始まります。
ひとつの季節がめぐるまでの「ニセモノ」の天山
人間の世界を知らない魂は、病院で死を迎えることになった中学二年生の天山の体に、ひとつの季節がめぐるまでという期間限定で入り込むことになります。そして改めて天山として目覚めたときには、名前も過去も思い出せず、記憶喪失の状態。「ニセモノ」の天山として親友の卓真や周囲の助けを受けながら学校に通いはじめます。
些細な日常も感情に溢れている
生き返った天山の体を借りて、様々な初めての「感情」を体験していく魂。生きていれば当たり前に抱く感情を一つ一つ新鮮なものとしてうけ止め、お風呂に入ったり、プリンを食べたり、だれかの笑顔を見たりという些細な日常が楽しくて仕方ない様子にこちらも嬉しくなってしまいます。
移ろいゆくさまざまな感情
でも感情は移ろいやすいもので、出会う感情はもちろんポジティブなものばかりではありません。自分が以前はピアノを得意としていたことを知り、そのことを通して登校拒否中の女の子が抱える悩みと向き合うことになった魂は、生きていたときの天山に向けられている感情や行動に戸惑い、落ち込み、思い悩みます。
「生きる」ことの不思議さ、かけがえのなさ
そして、人と関わり、音楽と向き合いながら、「生きること」の喜びや切なさを味わう日々も期限付きのもの。再び春が近づいてきたころ、「天山」の体に異変が起こり始めます。
生きるとはどういうことか。苦しさや悲しさがあっても、それでも「この世を生きる価値がある」と思えるのはなぜか。普段考えてもみない切り口で「生きる」ということの不思議さやかけがえのなさが伝わってきます。
前作「杉森くんを殺すには」
長谷川さんは、前作の『杉森くんを殺すには』でも「生と死」についての物語を丁寧に書かれています。生きることと死ぬことは裏表ですが、「死」はほとんどの小学生にとっては馴染みがないもの。
タイトルに「殺す」という強い言葉が使われているため、一見物騒な印象を受けるかもしれません。実際、このインパクトのあるタイトルが目を引き、多くの子どもたちが手に取るきっかけとなっているようです。
「生きる」ことの不思議さ、かけがえのなさ
物語の語り手は高校生のヒロ。小学校からの親友だった杉森くんを殺すことにした、と義兄のミトさんに告げると、「今のうちにやりのこしたことをやっておくこと」「どうして杉森くんを殺すことにしたのか、きちんと言葉にしておくこと」とアドバイスを受けます。
事前情報なしで読んでみてほしい1冊
ヒロの一人称の淡々とした語りで始まり、話が進むごとに少しずつ明かされる真実。テーマの重さを感じさせない軽やかな筆致で、解説まで一気読み間違いなしですが、ぜひこれ以上の事前情報なしで読んでみてほしい1冊です。
学校では教えてくれないこと、今すぐに必要がなくても知っておいた方が良いことも書いてあります。この本がたくさんの大人にも読まれることで、必要としている子どもたちに届きますように、と願うばかりです。