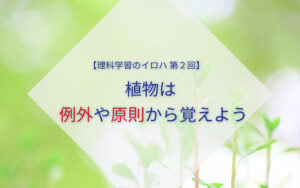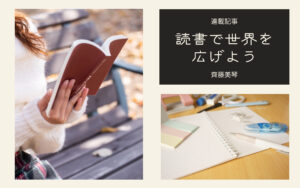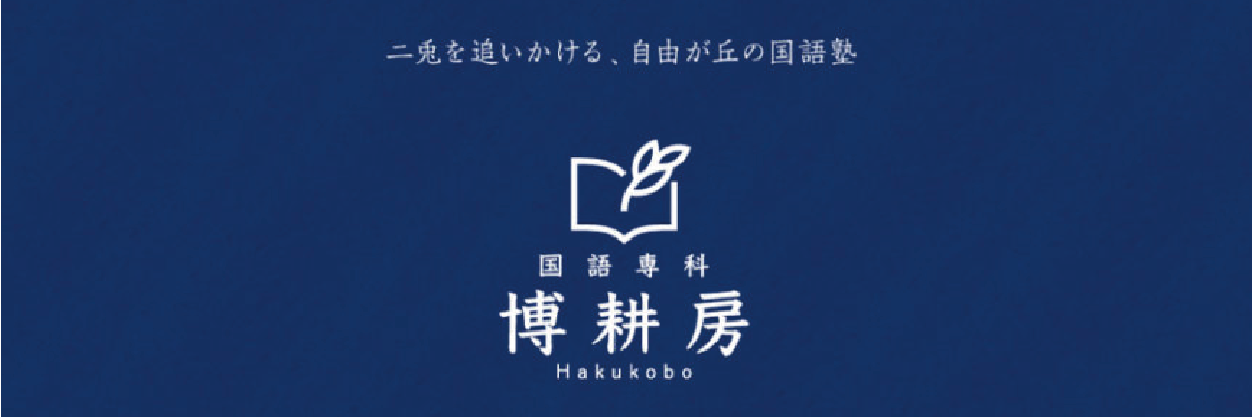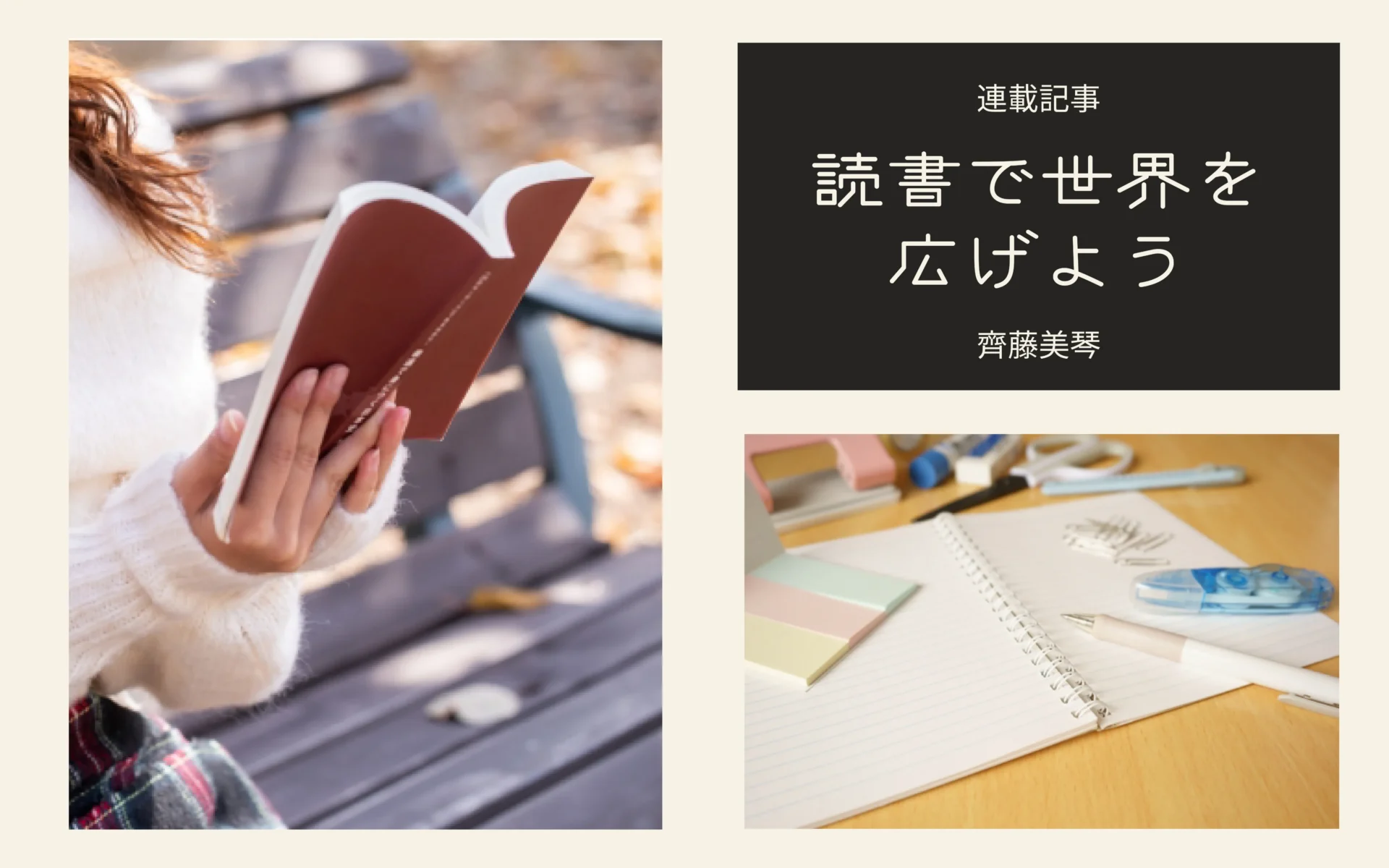
読み継がれる名作を読書の入口に
「文学の名作」というと、大人向けで難しい、あるいは教科書でしか出会わないもの、という印象を抱く方も多いかもしれません。しかし、子どもたちに物語に入り込みやすい形で手渡すことができれば、名作はむしろ「読書の入口」になります。
絵本の延長としての読書体験におすすめの「100年読み継がれる名作」
世界文化社の「100年読み継がれる名作」はその好例で、単行本よりも一回り大きなページに総ルビ、本ごとに異なるイラストレーターによる親しみやすい挿絵で、絵本の延長としての読書体験におすすめのシリーズです。
難しい言葉の説明がついているのもおすすめのポイント
そして小学生へのおすすめのポイントは、本の上下どちらかに難しい言葉の説明がついていることです。
注釈にあるちょっとした言葉の助け舟が、読むときの良き先導役になってくれるのです。
今回は、シリーズの既刊10冊の中から、新見南吉、芥川龍之介を取り上げてご紹介します。
新見南吉『でんでんむしの悲しみ』 詩『明日』
『ごんぎつね』、『手袋を買いに』などの童話で知られる新美南吉は、生まれ育ったふるさと、愛知県半田市の豊かな自然を舞台にしたあたたかみのある作品が多い一方で、病とともにあった20代の作品には、どこか寂しさを帯びたものが多くありました。
殻の中に悲しみを背負って生きるかたつむりが主人公の『でんでんむしの悲しみ』
初めて喀血した22歳のときに書かれたとても短い童話、『でんでんむしの悲しみ』は、殻の中に悲しみを背負って生きるかたつむりが主人公です。短く言葉もやさしいため一年生からでも読めますが、その内容は深く哲学的です。
自分だけが不幸だと思い込んでいたでんでんむしは、実は仲間たちもそれぞれに悲しみを抱えていると知り、「悲しみはだれでももっているものなのだ」と悟ります。こちらは、当時の南吉自身の心にあった寂しさが素直に表れた作品と評価されています。
コロナ禍に朗読されていた詩『明日』
また、巻末に収められた詩『明日』では、自然を通して明日への希望を明るく優しく歌い上げ、読む人の心を静かに照らします。愛知県半田市の新美南吉記念館では、コロナ禍にこの詩が朗読されていたそうです。
南吉の作品にある言葉は、子どもにあわせた目線でありながらも、すべての人に寄り添う優しさを持っています。
芥川龍之介『鼻』 解説付きの楽しみ
芥川龍之介の作品は、教科書にも収録されている『蜘蛛の糸』や『羅生門』が馴染みやすい作品として知られています。中学受験塾のテキストで『トロッコ』が扱われていることも多く、読んだことのある小学生も多いはずです。
人の心の内面を上手に書き出した『鼻』
もし、先に挙げた作品しか読んだことがないならば、『羅生門』と同時期に書かれた『鼻』をお薦めします。
『鼻』の主人公の禅智内供は、人並外れて長い鼻を恥じ、どうにかして短くならないかと悩み続けています。ついにある方法で鼻を短くすることに成功し、もう人に笑われずに済むと喜びますが、その喜びも長くは続かず、、と、人の心の内面を上手く書き出した作品です。
古典的な題材を近代の感覚で書き直した作品
実は、この物語は『今昔物語集』や『宇治拾遺物語』に収められた説話から着想を得ており、古典的な題材を近代の感覚で書き直したものだそうです。大正初期、芥川は、師と仰ぐ夏目漱石にこの作品を読んでもらおうと書き上げ、実際に漱石の目に留まって絶賛されたことで若くして人気作家としての第一歩を踏み出しました。
巻末の解説にはそうした背景、逸話が書かれており、これらを踏まえて読むとただのユーモラスな逸話ではなくいっそう味わい深く感じられます。
次の世代へのバトンとして
新見南吉も芥川龍之介も、どちらも生まれてから既に一世紀以上が過ぎています。でも、常に新しいものが溢れる今の世の中だからこそ、読み継がれる名作のような変わらない価値あるものに目を向け、次の世代へつないでいくことを大切にしたいものです。
わたしたち大人世代が、このような本を「読書の入口」として子どもたちに手渡すことができれば、文学は決して遠いものではなく、日常に寄り添ってくれる豊かな糧となってくれることと思います。


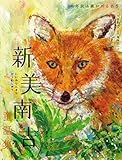


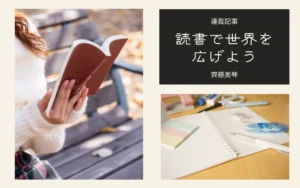



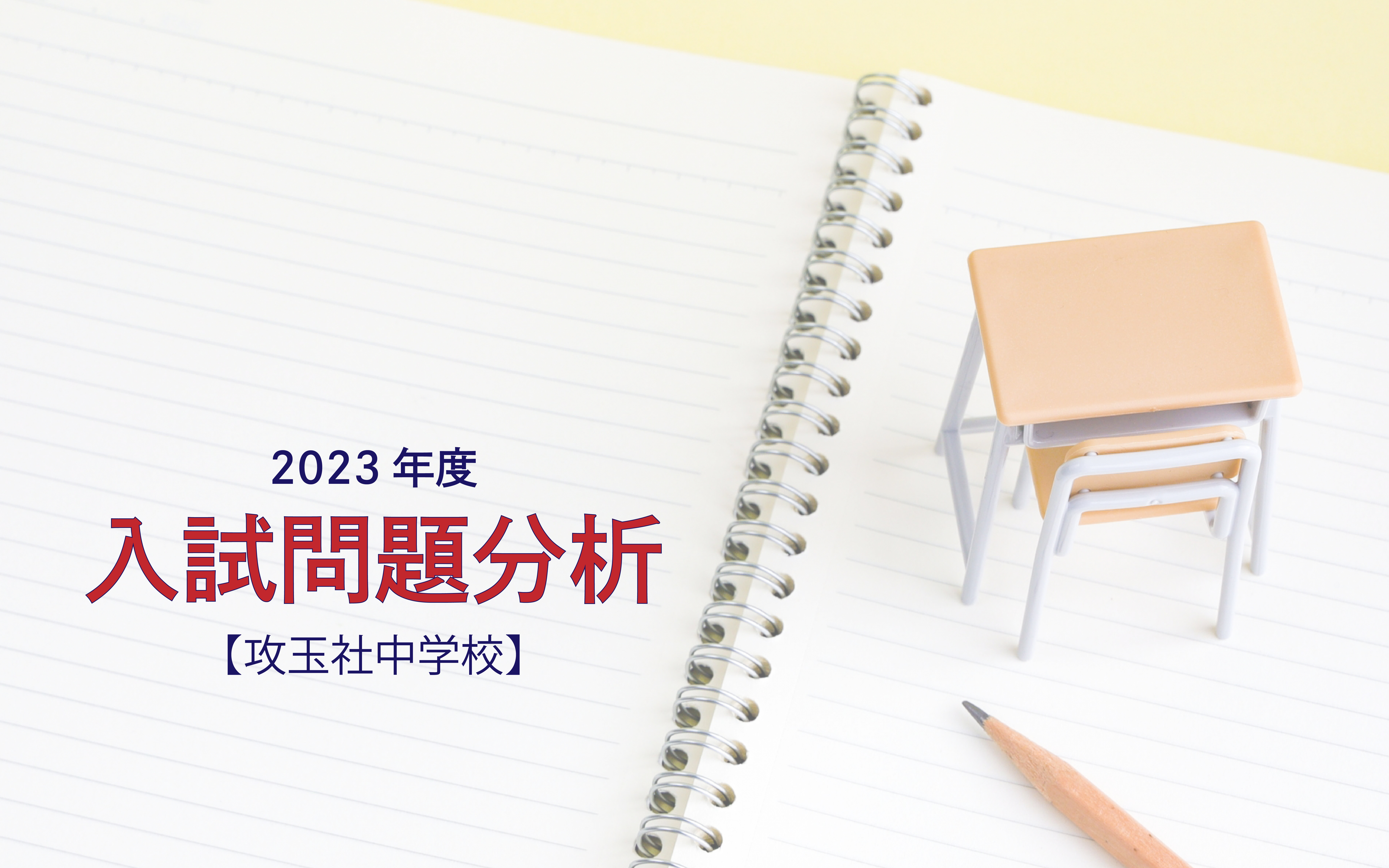
![塾の小窓をのぞいたら――矢野の雑記[2024年01月01日ー01月03日]](https://www.cj-atelier.com/wp-content/uploads/2022/01/eyecatch_yano-150x150.jpg)