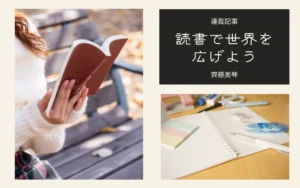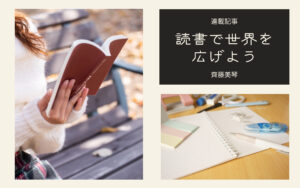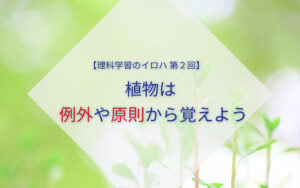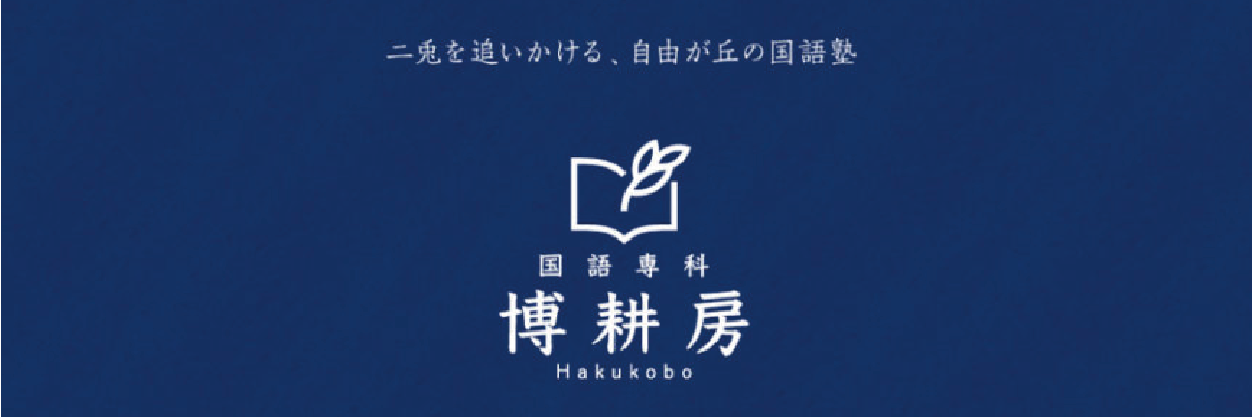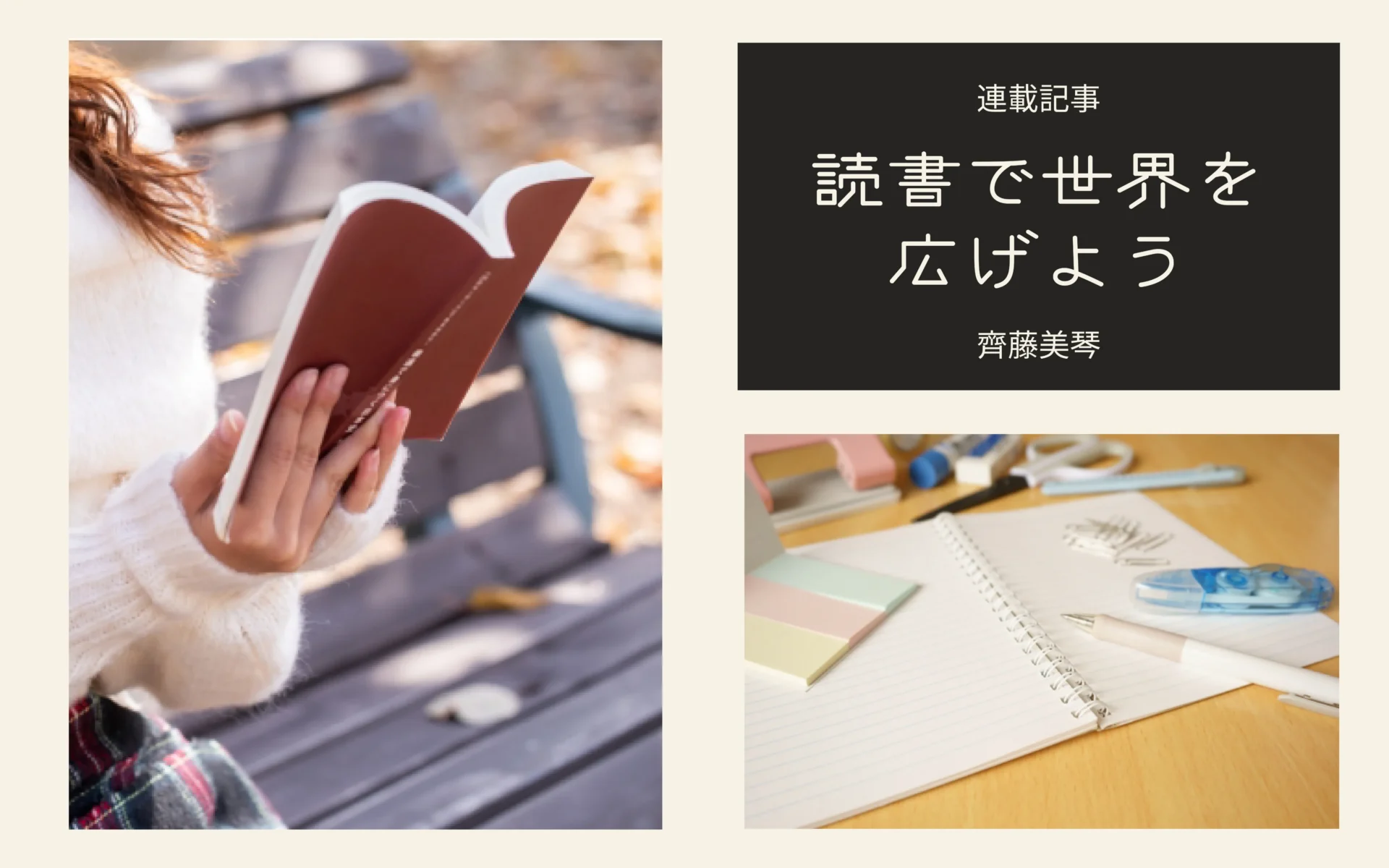
人間と自然の関わり
朝夕はひんやりとして、あれだけ暑かった夏が嘘のようです。季節が確かに移ろったことを肌で感じながら、その変化の背後には自然の大いなる力があることに気づかされます。
今回は、中学入試の論説文の頻出テーマである、人間と自然の関わりについてわかりやすく触れられる本を紹介します。
宇根豊『日本人にとって自然とはなにか』
「人間にとって自然」とは何か」題名として掲げられたこの問いはあまりに大きく、時代や文化によってその答えは変わってきました。人間と自然との向き合い方について取り上げた本書は2019年の発刊から、中学入試の入試問題や模試で数多く取り上げられています。
日々田畑に立つ研究者だからこそ生まれる説得力
筆者の宇根豊さんは、ご本人の言葉を借りるなら「百姓」でも研究者でもあり、研究者としての分析にとどまらず、日々田畑に立ち、草木や虫とともに暮らす日々から生まれる言葉は、理論よりもずっと説得力を持っています。
そして、自然を単なる「資源」とみなすのではなく、人と同じように魂を持つものとして捉えるアニミズムの感覚に目を向けます。川や山、木や虫といった存在に「神」を見出す視点は、八百万の神々を祀る日本の宗教観とも重なります。
自然への畏敬の念と宗教観
宇根さんが強調するのは、「自然は人間が支配するものではなく、畏れ敬う対象だ」という姿勢です。たとえば田んぼひとつとっても、稲を育てるのは人の力ではなく、水や土、天候といった自然の働きがあってこそ。この自然と向き合う際の謙虚さが、長く日本人の生活文化を支えてきました。
日本の自然観と西洋の自然観
日本の自然観は西洋と比べるとよりわかりやすく、土台となる考え方から大きな違いがあります。日本の自然観は、人と自然を切り離さず、同じ世界に共存する仲間として受け止めます。神社の森や祭りの習俗が今も残っているのは、その信仰の延長にあります。

一方で、西洋の自然観は、キリスト教における「神」とその神が創造したものの区別を前提としています。自然は人間が与えられ、利用すべきものとされることが多く、その結果、自然は征服するものであり、開発の対象として扱う歴史が生まれました。(この日本と西洋の自然観の対比を、知識として知っておくだけでも論説文が読みやすくなることがあります。)
里山から未来へ
日本人の自然観を考える上で、もう一つ鍵となるのが「里山」という身近な風景です。森と田畑のあいだに広がる里山は、単なる生活の場ではなく、人と自然が互いに働きかけ合い、均衡を保つ場でした。
人が木を伐り、落ち葉を肥料に使い、また森を守るというように、人が適度な介入をすることで自然は荒れることなく豊かさを保ち続けます。自然を畏れ、敬い、受け入れる。そんな日本人の感覚は、環境問題が深刻化する今日の世界においても、普遍的な価値を持つのではないでしょうか。
里山を近くに感じる絵本:今泉光彦『さとやまさん』
最後に、子どもたちが、そんな里山を少しでも近く感じるきっかけとなればと、1冊の絵本を紹介します。
日本の自然観と西洋の自然観
絵本の舞台は、滋賀県琵琶湖の西岸に広がる田園で、今泉さんはこの田園に魅力を感じj、40年も写真を撮り続けているといいます。
言葉は全編ひらがなで書かれ、「さとやまさんにあいにいこう」と読者に優しく誘いかけます。言葉が少ないからこそ、写真を通して感じる自然の豊かさをたっぷり味わうことができます。
自然と共に生きてきた背景を、新しい学びの出発点に
日本人が長い年月をかけて培ってきた、自然と共に生きることに重きを置く自然観。小学生にとっては少し難しいテーマかもしれませんが、こういった本をきっかけに古来の自然と人間の関わりの背景を踏まえ、新しい学びの出発点にしてほしいと思います。