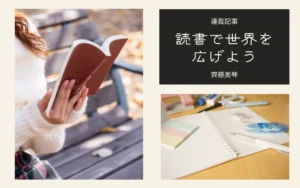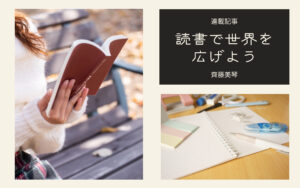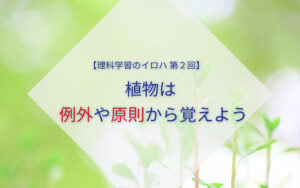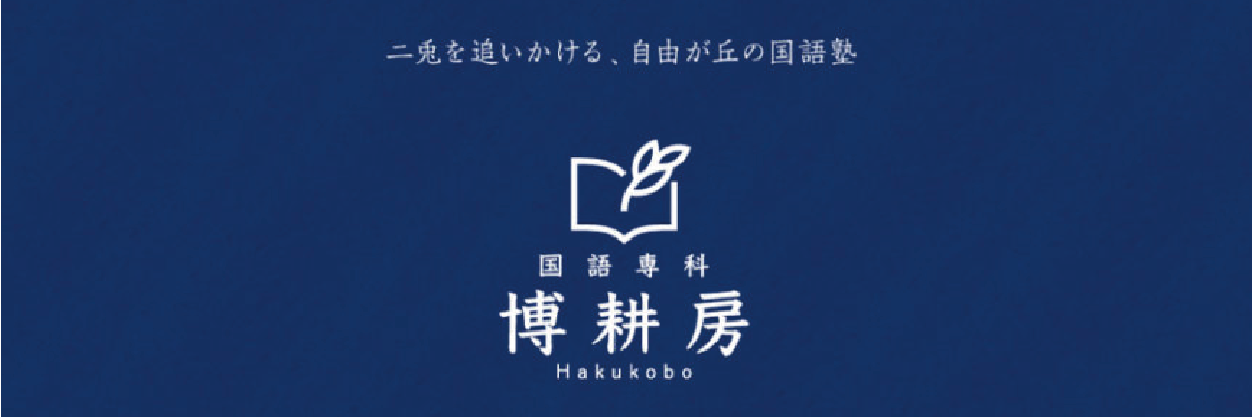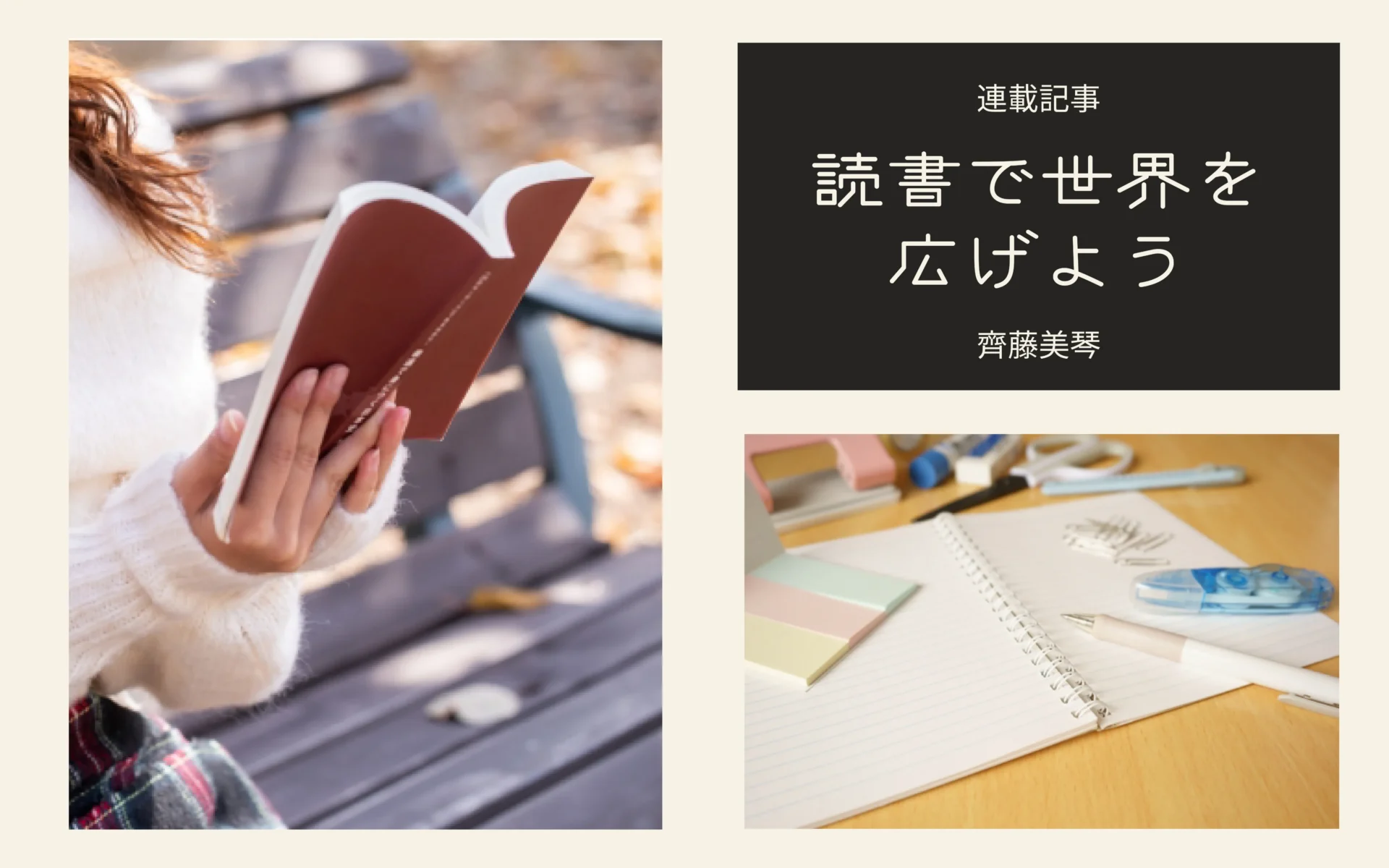
良い本環境に訪れる習慣作りを
読書の秋、ということで書店をはじめ各所で読書啓蒙の案内をよく見るようになりました。中学受験を考えるご家庭からは「読書は大事だと思うけれど、どんな本を読ませたらいいかわからない」「受験にも役立つ読書ってあるの?」という声を多くいただきます。
本選びは良い本を与えようと構えてしまうと悩ましいものですが、役に立つ本、難しい本を読ませることを目的とせず、日常の中に本との出会いを自然に増やすことを意識してみてください。
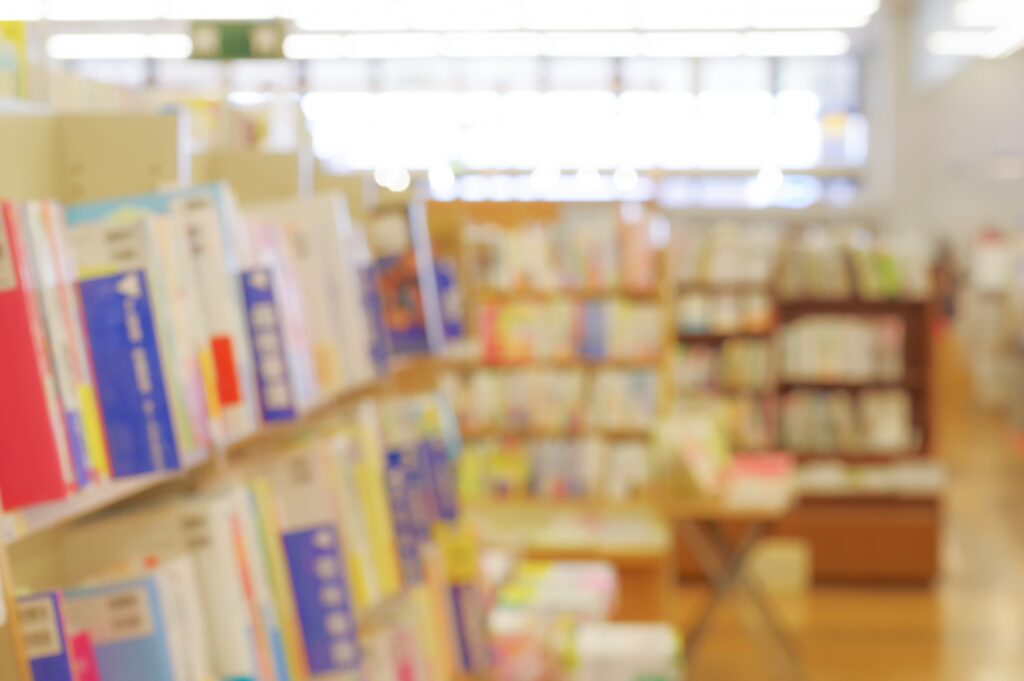
良い読書習慣は「本がある場所に定期的に行くこと」から
良い読書習慣の第一歩は、「本がある場所に定期的に行くこと」です。
どんなに良い本も、手に取るきっかけがなければ触れることができません。塾や学校とは別に、親子で本と出会う時間を生活の中に組み込んでみてください。たとえば「月に一度は図書館で過ごす時間をとる」「習い事の帰りは本屋さん」というように、イベント化してしまうのも効果的です。
大切なのは「読むことを強制しない」こと
このとき大事なのは、「読むことを強制しない」こと。本を選ぶ、手に取る、ページをめくって眺めてみる、その一連の行為そのものが、子どもにとって良い刺激になります。新しい物事への興味や好奇心はこうした自然な積み重ねの中で少しずつ伸びていくように思います。
図書館活用のすすめ
子どもの読書の幅を広げるうえで、図書館はとても頼もしい場所です。図書館では「読む」よりも「眺める」時間をたっぷりと取ってほしいと思います。子どもたちは、ぱらぱらとページをめくるだけでも、印象的な言葉や絵から自分なりに興味の入口を見つけていきますし、自分の目で見て「気になる」と思った本は、内容が難しくても意外と読めることがあります。
司書さんに尋ねてみるのもおすすめ
司書さんに「〇〇についての絵本を探しています」と声をかけてみるのも良い方法です。プロの目で、年齢や興味に合った本を紹介してくれます。
借りる本の中には「少し背伸びした本」を混ぜる
借りる本の中には、大人が選んだ少し背伸びした本を何冊か混ぜるのもおすすめします。自分が扱えるレベルの知識と少し先の知識を両方手にすることで、そこにつながりがうまれます。
借りてきたけれど結局読まなかった本というものが出るかもしれませんが、本を自分で選んだという行為が、子どもの自己肯定感や探究心につながりますから、無駄になるなど思わずにたくさんの本に触れてくださいね。
テーマを決めて横断的な本選び
読書は本来自由に向き合うものであってほしいと願いながらも、敢えて「受験にも役立つ本選び」があるとすれば、ポイントは「テーマを決めて横断的に本を探す」ことです。
学校や塾で習った分野やキーワードを軸に、色々な棚から本集めをするイメージです。今回は理科の授業で「人体」を習ったとして、横断的な本選びの例をご紹介したいと思います。
- 絵本を用いてやさしい視点から導入
かこさとし『たべもののたび』童心社
初版が1976年のロングセラー絵本です。食べ物たちが黄色い栄養のカバンを片手に人体を旅します。咀嚼されたあとに通る食道は「ももいろのトンネル」、「いぶくろこうえん」や「しょうちょうのジェットコースター」と消化器官の表し方も楽しいです。食べられる側の目線で、食べ物の摂取から排泄までのプロセスがわかりやすく描かれています。 - 児童向け読みものを通して物語として理解
『からだのしくみを学べる!はたらく細胞 人体のふしぎ図鑑』講談社
人気漫画の『はたらく細胞』のシリーズの読み物として人体のしくみを楽しく学べる一冊です。アニメの世界観をいかし、アニメイラストを2000枚以上使用。免疫細胞や赤血球などのはたらきを、アニメの印象的なシーンになぞらえて紹介しています。漫画やアニメから興味をもった子はもちろん、理科の知識を広げたい子にもぴったり。全編ふりがなつきなので、一度興味を持てば自分で読み進めることができるはずです。イラストに助けられて、体の中で起きていることを自然と理解できる構成になっています。
- 図鑑で専門的な知識を視覚で確認
『学研の図鑑LIVE 人体 新版』学研
〝これはぜんぶ、きみの物語″というメッセージを込めて作られた学研の図鑑。読者自身と重ね合わせてイメージしてもらうため、「食べる」「考える」など子どもたちが生活しているシーンの写真が各所にちりばめられ、図鑑全体がつながりをもった人体と同じイメージになるように、階層性を意識した配置になっています。図鑑は、どの出版社のものも工夫が凝らされていますが、こちらの『学研の図鑑LIVEシリーズ』は図鑑LIVEの編集長をつとめる松原さんの「感動を伝えたい」というこだわりが詰まっており、おすすめです。
こういった具合に、違う棚から同じテーマに関する本を集めてみます。理科の知識が物語や言葉とつながることで、「勉強=教科書」ではなく「学び=世界全体」という感覚が芽生えるのです。
中学受験に向けた読書も「知るって楽しい」が原点
中学受験に向けた読書というと、「知識を増やすため」「語彙を増やすため」と考えがちですが、根っこにあるのは「知るって楽しい」という気持ちです。その小さな芽を育てるために、図書館や書店などたくさんの本に触れられる場所をぜひ活用してみてください。
「本を読む子」にするのではなく、「本と自然に出会える環境」を整えることこそが、受験にもその先の学びにも生きてきます。読書の秋、お子さんと一緒に、世界を少し広げてみませんか。