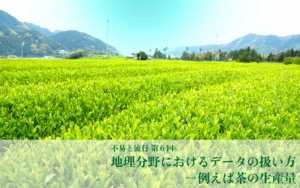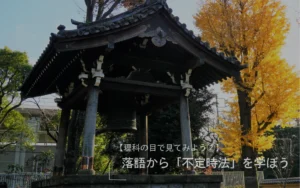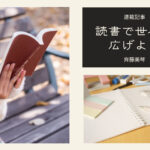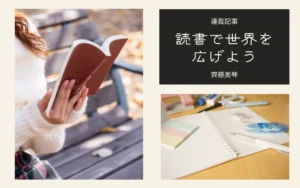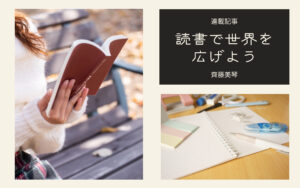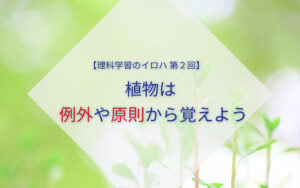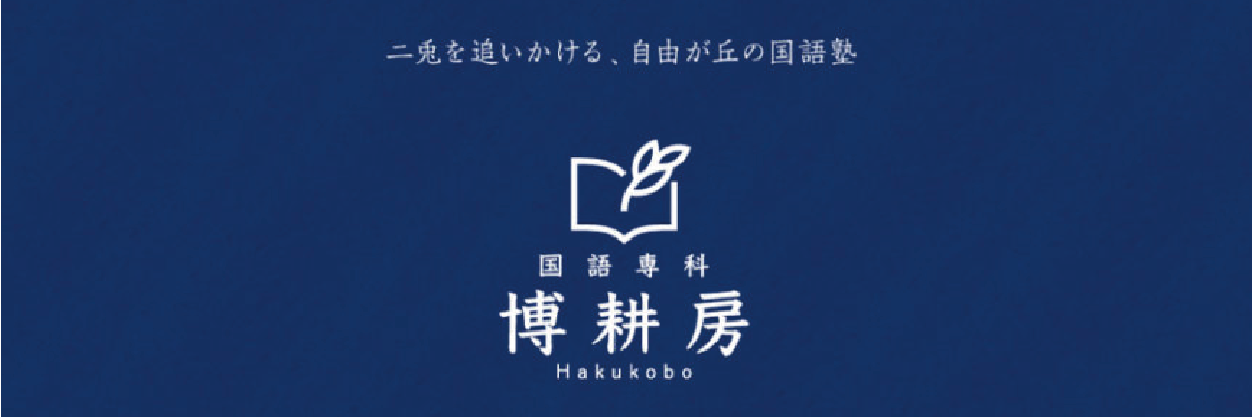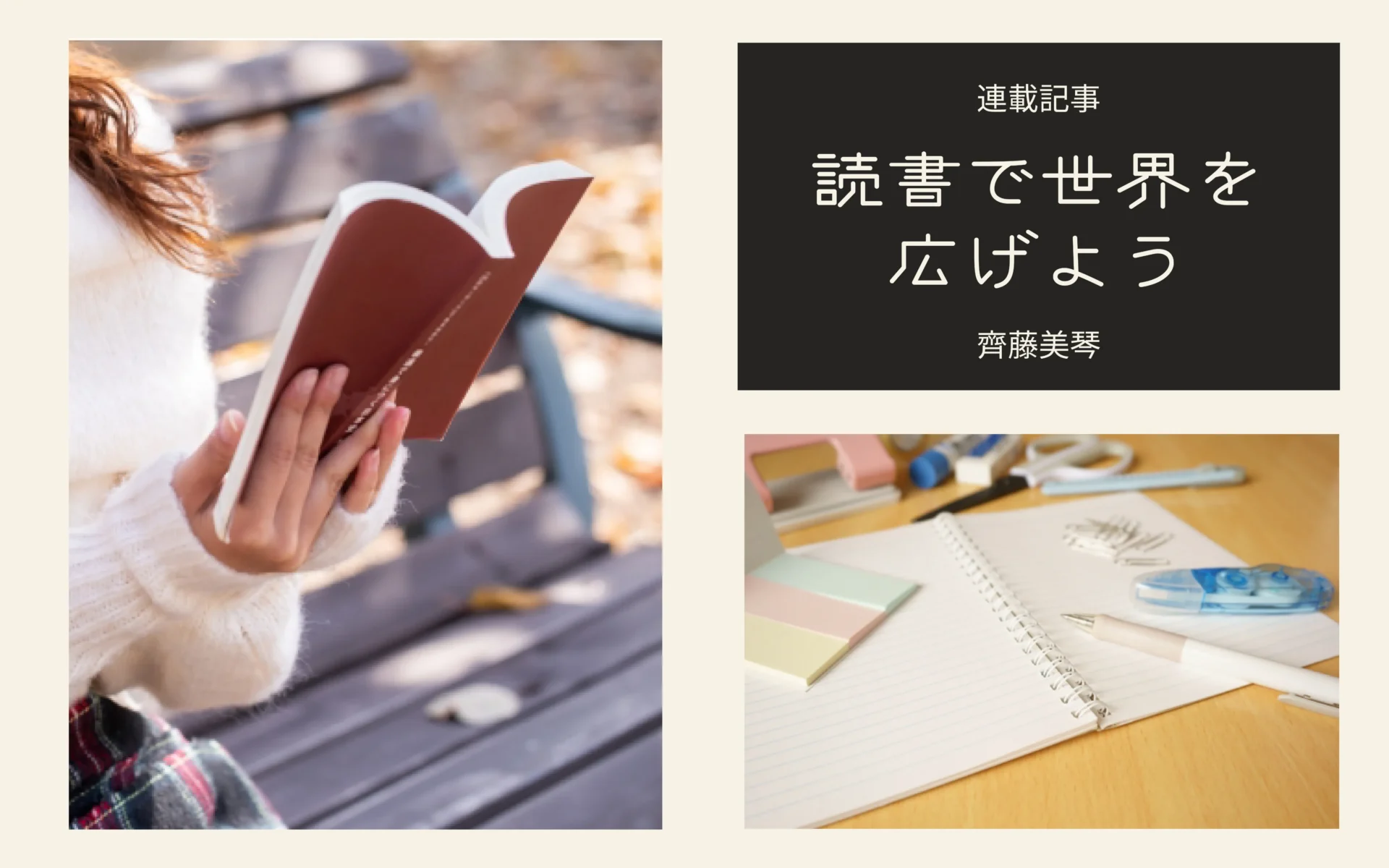
301話から選りすぐりの昔話
今回は 、1995年に刊行されたロングセラー『日本の昔話』全五巻に収録された301話より、選りすぐりのお話をまとめた、『よりぬき 日本の昔話』を紹介します。
長年にわたって親しまれてきた前シリーズは、日本全国からのお話の収集、そして標準語への「翻訳」という10年以上の年月をかけて編集された珠玉のお話集です。その良さを残しながら、できるだけ多くの子どもたちに手に取りやすい形に再編されたのが今回の2冊です。
第一線で活躍中のイラストレーターによる挿絵
『日本の昔話』では、赤羽末吉さんの味わい深い絵が特徴でしたが、今回は第一線で活躍中のイラストレーターたちの個性豊かな挿絵が添えられ、お話の世界がより鮮やかに広がります。 YA(ヤングアダルト)小説の表紙画でも大人気のカシワイさんの絵も見つけました。
伝承すべき大事な文化財として
日本の昔話は、長い年月をかけて人々の口から口へと語り継がれてきた文化の宝です。30年前の日本には、東北地方を中心に伝承的な語り手がたくさんいらっしゃり、語りの文化が日常にあったといいます。
そこで語られる一つ一つのには自然との共生や、知恵と勇気、笑いや哀しみといった、時代や地域を超えて通じる人間の営みが詰まっています。昔話を読むことは、単に昔の話を知るだけでなく、日本の価値観や暮らしの知恵に触れることでもあります。
所持率が4割以下にまで減少した『ももたろう』の絵本
ところが最近は、昔話の名前は知っていてもあらすじはわからない、というような子どもたちが増えてきたように思うのです。筑波大学の徳田教授らが1990年から実施している調査によると、かつては8割の家庭が所持していた『ももたろう』の絵本は、2020年には4割以下にまで減少したといいます。
昔話を知らない子どもには、その話に由来する比喩表現やパロディが通じにくくなっています。せっかく目の前に素晴らしい文化財としての昔話があるというのに、共通の文化的背景や物語を持たないまま成長していくのは惜しいことではないでしょうか。
語りつがれてきた形のままに
本書には、「桃太郎」「かちかち山」「わらしべ長者」など、誰もが一度は聞いたことのある定番の昔話が収録されています。大人には懐かしさを呼び起こすものばかりですし、方言を生かした語りやリズムの良い文体が、その土地ならではの雰囲気を感じさせます。
本書では、「昔話の語り」を忠実に再話することが大切にされ、以下のような昔話の特徴をそのままに残しています。
- 同じような場面を同じ言葉やリズムで語り、3回の繰り返しを好む。場面や気持ちの説明はなく、早いテンポでストーリーが進む
- 昔話がフィクションであることをはっきりとさせるために「むかしむかしあるところに」というような決まり文句をいう。「どっとはれ」「とっぴんぱらりの、ぷ」など地方によって異なる結末句で終わる
これらは元々決まりがあったわけではなく、口承でたくさんの語り手によって繰り返し語られてきたことによって自然と生まれた語り方なのだそうです。
昔からの姿をそのまま変えずに語り継ぐ
また、知っているつもりの昔話であっても残虐なエピソードを切り取ってしまうなど、本来の姿と変わった形で絵本になっているものが多い中といいます。本書では、人間と自然が共生してきたこと、命はめぐるものであることを伝えていくものとして、昔からの姿をそのまま変えずに語られています。
昔話には、人の成長や自然との関係、命の尊さといった普遍的なテーマが説明こそされませんが、随所に内包されています。
子どもたちの耳に届きますように
今回の著者である小澤さんがあとがきに書かれた言葉には、「子どもたちの耳へ届くことを」と書かれています。本書はすべての漢字にルビが振られており、低学年であれば一人で読めてしまうものではありますが、大人が声に出して読み聞かせをすることで、馴染みのない言葉やリズムが自然と子どもたちに受け容れられるはずです。
昔話は、「語り」つがれてきたもの。子どもたちの一番近くにいる大人たちが、声でお話を届けてあげてほしいと思うのです。