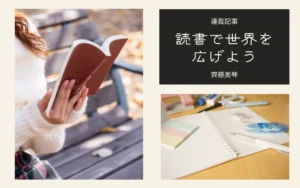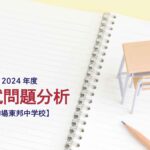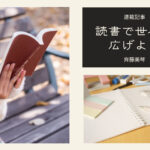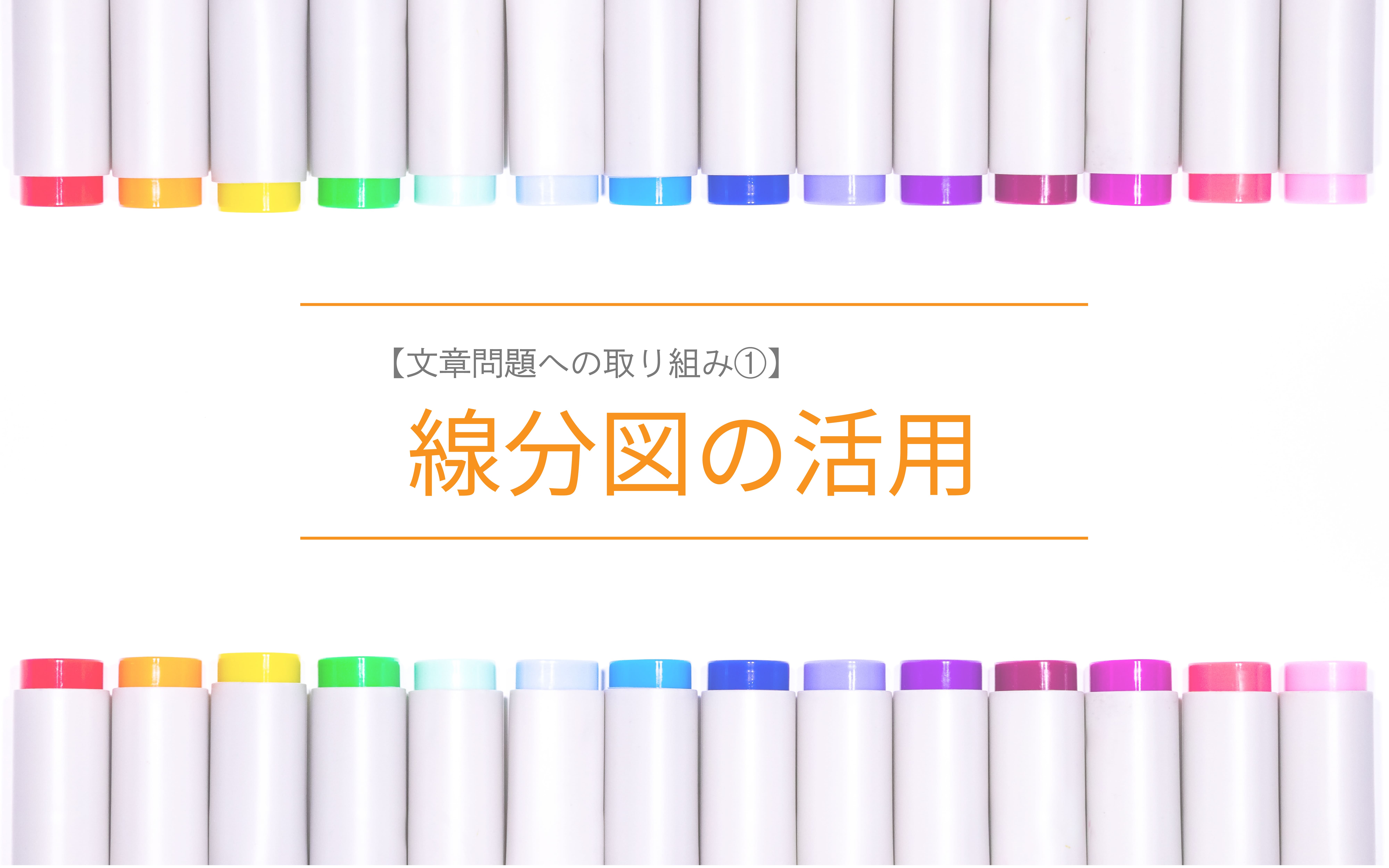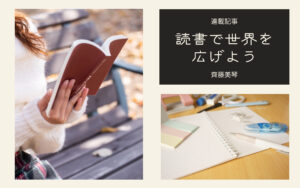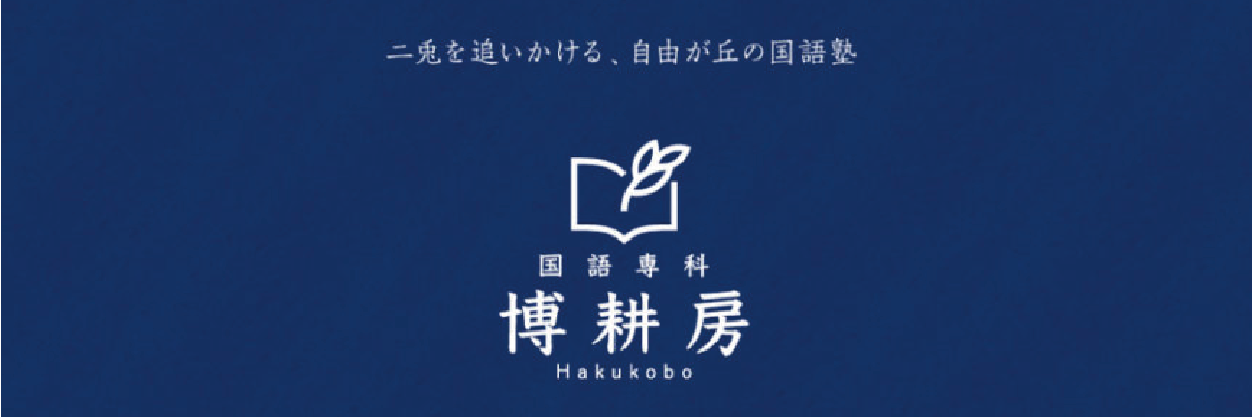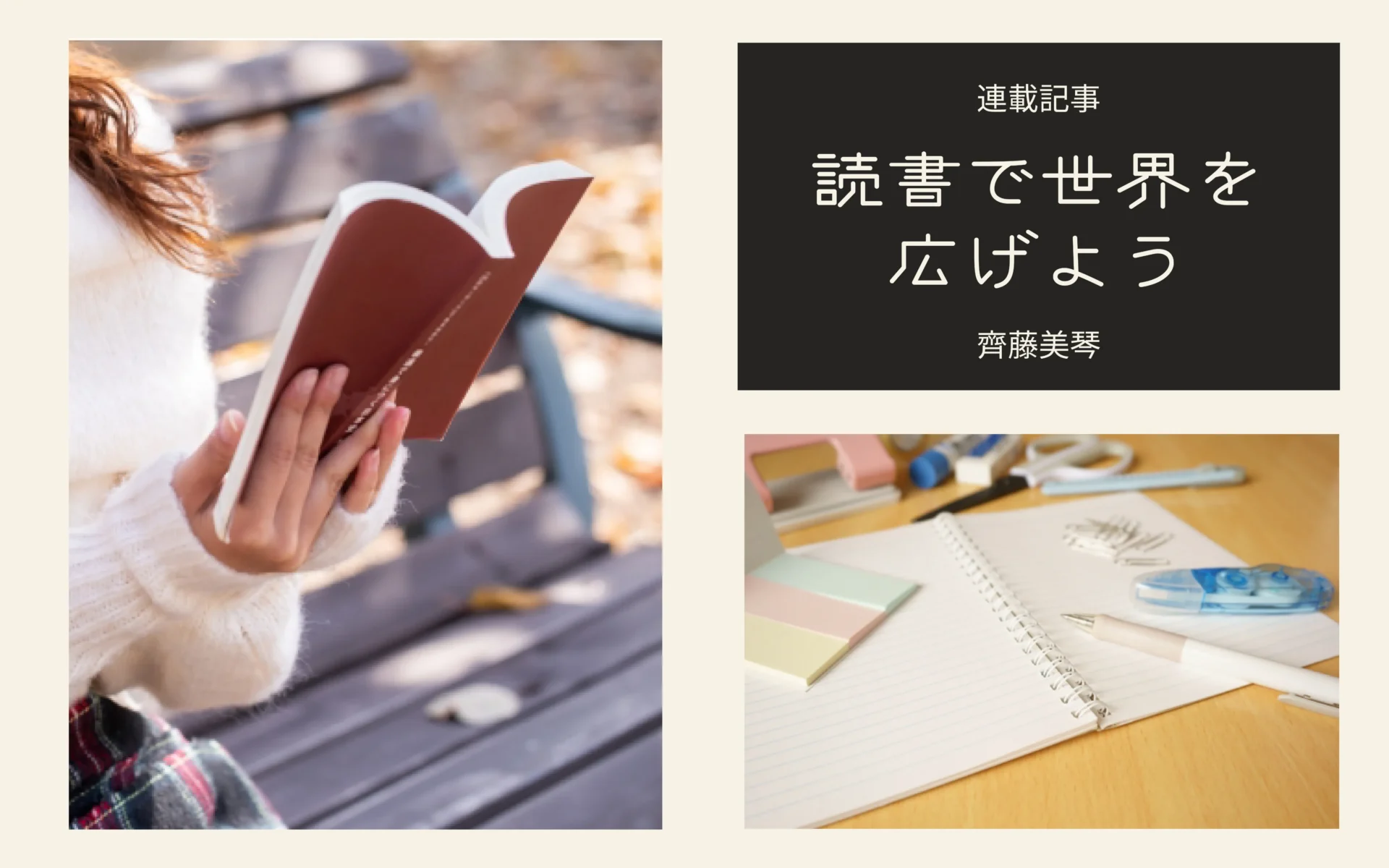
「ルビは好奇心のバリアフリー」
6月2日が「ルビの日」ということにちなんで、ルビ財団(一般財団法人ルビ財団)が発表した、記念すべき「第一回ルビフル大賞」に選ばれた作品を紹介したいと思います。
ルビ財団とは、「ルビは好奇心のバリアフリー」という言葉をスローガンに、社会にふりがな(ルビ)を適切に増やすことで、誰もが学びやすく、多文化が共生する社会づくりを目指す団体です。
「ルビフル大賞」2025グランプリ受賞作
今回、ご縁あってルビフル大賞の授賞式に立ち会うことができました。 ルビフル本大賞には、昨年度に出版された書籍のうち、通常はルビが振られないような内容にも関わらず意識的にルビを多く振られているもの、そういった著者や編集者の意思が表れているものが選ばれます。
そのような映えあるルビフル大賞2025グランプリに選ばれたのは、 Newton別冊『精神科医が語る 発達障害のすべて 改訂第2版』 、そしてサッカーの三苫選手が書いたドリブルの理論を解説した本『サッカードリブル解剖図鑑』の2冊です。
NEWTON別冊『精神科医が語る 発達障害のすべて 改訂第2版』
NEWTONは様々な専門的な分野についてわかりやすく解説してくれる雑誌ですが、この号ではほとんどの漢字にふりがなが振られています。
単に「読めるようにする」ための工夫ではなく、まだ難しい言葉に慣れていない子どもたちにも、知識への扉を開いてくれています。
ルビがあるから生まれる「読める」という安心感
発達障害というテーマは、自分やまわりの誰かに関係があるかもしれないものであるにもかかわらず、それを伝える言葉は、医学や心理学の専門用語が多く、子どもには理解しにくいと感じられることもあります。
ルビがあることで、まずは「読める」という安心感が生まれ、読めるからこそ、内容にも少しずつ心を向けることができ、自分なりの理解につなげていけます。 専門書であるにもかかわらずルビがあるというのは、「知ることに年齢の制限はない」というメッセージとも受け取れます。
三苫薫『サッカードリブル解剖図鑑』
こちらはタイトルの通りサッカーのドリブルに特化した専門的な本ではあるのですが、図解のテクニックだけではなく、三苫選手がそれぞれのシチュエーションでどのような思考をしているかなどの言語化にもこだわっているので、読み物として楽しむことができる本になっています。
サッカーに興味がある子供たちにとっては夢のような1冊ですね。三苫さんの、子供のヒーローになりたい、日本のサッカーの未来に貢献したいという思いが伝わってきます。
出版社としては、ルビを振ることで子どもだけのための本に見られてしまうのではという葛藤もあったそうですが、それを越えて、「好きだからもっと知りたい」と言う気持ちを 大切にしてほしいとお話されていました。
ルビがあることで、読み進められる楽しさを
子どもたちにとって、本にルビがついていることで本の世界はぐっと身近になります。知らない漢字があっても読み方がわかれば、そこで立ち止まることなく物語を追いかけることができ、自分の力で読み進める楽しさを感じられます。
たとえまだ漢字に慣れていない子でも、「読める」という小さな成功体験を重ねることで、本を読むことそのものが楽しくなることもあるはずです。
本の面白さに触れる前に文字の壁が立ちはだかる
逆に、読み方がわからずに物語の流れが途切れてしまうと、先に進むことをあきらめてしまうことも少なくありません。 本の面白さに触れる前に文字の壁が立ちはだかってしまうのです。
本をなかなか手に取らない子どもでも漫画ならば読もうとするのも、絵が助けてくれる事はもちろんのこと、全てにルビが振ってあることで、読み進めたい気持ちを削がれることなくページをめくれるからでしょう。
「読める」本がある環境が世界を広げます
ルビ財団のファウンダーである、マネックスの松本大さんの幼少期のエピソードはとても興味深いものでした。
その頃は目の前にあるから手に取るだけだった本が、結果的に興味の深掘りにつながったのです。
「知らないから、読まない」ではなく、「知らないけど、読んでみよう」と思える環境へ
「知らないから、読まない」ではなく、「知らないけど、読んでみよう」と思える環境が、子どもたちの読書を豊かにしていきます。
子どもの興味関心に、大人が「これはまだ早い」と制限をかけてしまうのはもったいないことです。子どもから大人まですべての人へという思いの表れですね。 ルビがあるからこそ届く本にたくさん出会って欲しいと思います。