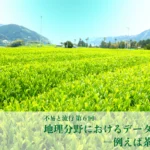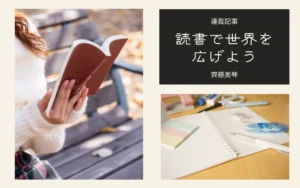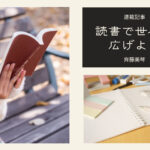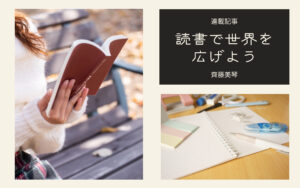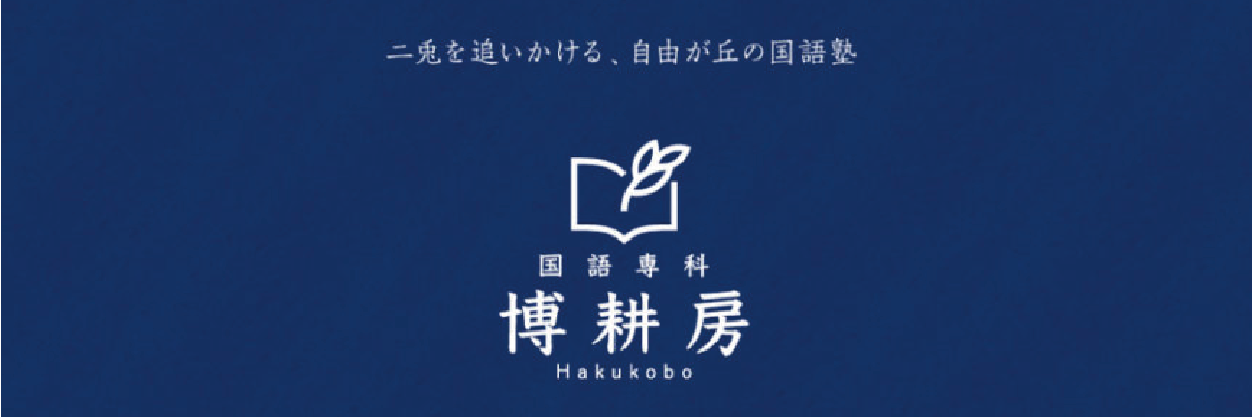2025年春、東京ではあっという間に桜の季節が終わりましたね。
今年の春はやや肌寒い日が続きましたが、桜が散り始めると少しずつ春らしい暖かさを取り戻してきたように感じます。夜風はまだ涼しく、寒暖の差に困ることもありますが、日中は半袖でも過ごせるようになってきました。
「抹茶アイスが食べたい」と思う季節ですね。もちろん、バニラでも、チョコでも、バナナチョコアイスでも構いませんが。個人的には「渋甘い」濃厚な抹茶アイスが好きです。
抹茶と言えば京都、とくに南部に位置する宇治市が産地としてよく知られています(社会科的には、世界文化遺産の「平等院鳳凰堂」も大切ですが……)。他にも福岡県八女市、愛知県西尾市などで抹茶がさかんに生産されています。
変化が見られる荒茶の生産量・生産地
また、暑くなってくると水分補給も大切です。私は真夏でも温かいコーヒーばかり飲んでいるのでやや変な人かもしれませんが、一般的には外出時に水筒を持参したり、外でペットボトルなどを買ったりするのでしょう。

日本人にとって、お茶はなじみの深い飲み物ですね。コンビニや自動販売機にはたくさんのお茶系のペットボトルが並び、私たちの日常生活にはとても身近な存在であり続けています。ちなみに、お茶のペットボトルは1990年から販売が開始されたようです。現在ではさまざまな銘柄があるので、お好みが決まっている人もいるでしょう。かくも身近なお茶ですが、実は日本の他の農産物と同じように、荒茶の生産量は減少傾向にあります。
荒茶の生産量で静岡県を抜いて日本一になった鹿児島県
そうしたなかで、2025年2月には「静岡県を抜いて、鹿児島県が初めて荒茶の生産量で日本一になった」というニュースが各メディアで報じられ、大きな話題になりました。

鹿児島県は調査開始後初めての1位で、これまでは静岡県が65年連続で日本一だったのです。それだけにこのニュースの印象が強かったようで、子どもたちもよく覚えているのですが、受験生にとっては困った状況になりました。
中学入試の地理分野の出題傾向
近年の中学入試における社会科の問題、とりわけ地理分野においてはデータを使った問題は難度が高く、各校の入試問題作成者の工夫が各所に見られます。データも、国の機関などが公表している情報から直接入手し、作問に活用していることが多々あります。
主に『日本国勢図会』『データでみる県勢』『日本のすがた』から出題される
しかし、一般的には中学入試で扱う地理の各種データ類は、主に『日本国勢図会』『データでみる県勢』『日本のすがた』から引用されます(いずれも「矢野恒太記念会」刊行)。
これらは12月から5月にかけて出版されますが、最新のデータとして紹介されている数値は概ね2年前、もしくは3年前のものです。その理由は、膨大なデータの集計に時間がかかったり、書籍の編集のタイミングだったりするためで、必ずしも最新のデータが反映されているとは限りません。
よって、最新版『日本のすがた2025』でも、茶の生産量は2023年のデータになっており、1位は静岡県、2位が鹿児島県となっています。
データを用いた時事問題や関連知識を問う問題が出題される
では、これらのデータは入試問題ではどのように扱われるでしょうか。単純な知識問題として生産量の順位を問う形式は、受験生の混乱を招くことになるのでおそらく出題されないでしょう。時事問題として出題されるか、もしくは設問の入り口になるリード文などで紹介され、関連した知識が問われると予測します。
例えば、
2025年2月に、静岡県を抜いて初めて鹿児島県が茶の生産量1位(2024年)になったという報道がありました。調査開始以来、初めての日本一です。ペットボトル用の茶葉の出荷が多かったことなどが理由ですが、鹿児島県では茶の生産量が増えています。その理由を、地形に関連させて簡潔に説明しなさい。
【解答例】
鹿児島県では主に平坦なシラス台地など広大な台地で茶の生産がおこなわれているため、機械化が進んでいるから。
今回と似た状況は、インドが中華人民共和国を抜いて人口世界一になったときにも見られました。このときもニュースでの報道が先行し、書籍等々での正式なデータの公表はあとになっていましたが、入試においては時事問題的な扱いばかりで、大きな混乱もなく終えています。
日本における「茶」の歴史
ちなみに、日本における茶の記録は奈良時代から見られ、鎌倉時代に臨済宗の開祖である栄西が日本初の茶の専門書「喫茶養生記」を著します。その後、華厳宗の明恵上人が京都北部の高山寺に日本で初めての茶園を開き、少しずつ日本でも茶の栽培が始まりました。
室町時代から安土桃山時代にかけては社交の一つとして「茶の湯」が武士の間で流行し(織田信長や千利休がよく知られています)、江戸時代になってようやく庶民にも広がっていったようです。そして、茶葉は江戸時代末の開国後(1858年日米修好通商条約)には、生糸に次ぐ貴重な輸出品でした。
地理の各種データを覚えるのは大変ですが、野菜や果物などは日々の食事、給食などで触れることが多いので、生活のなかで少しずつ覚えられると良いですね。
美味しい抹茶アイスが食べたいと思う、大森でした。